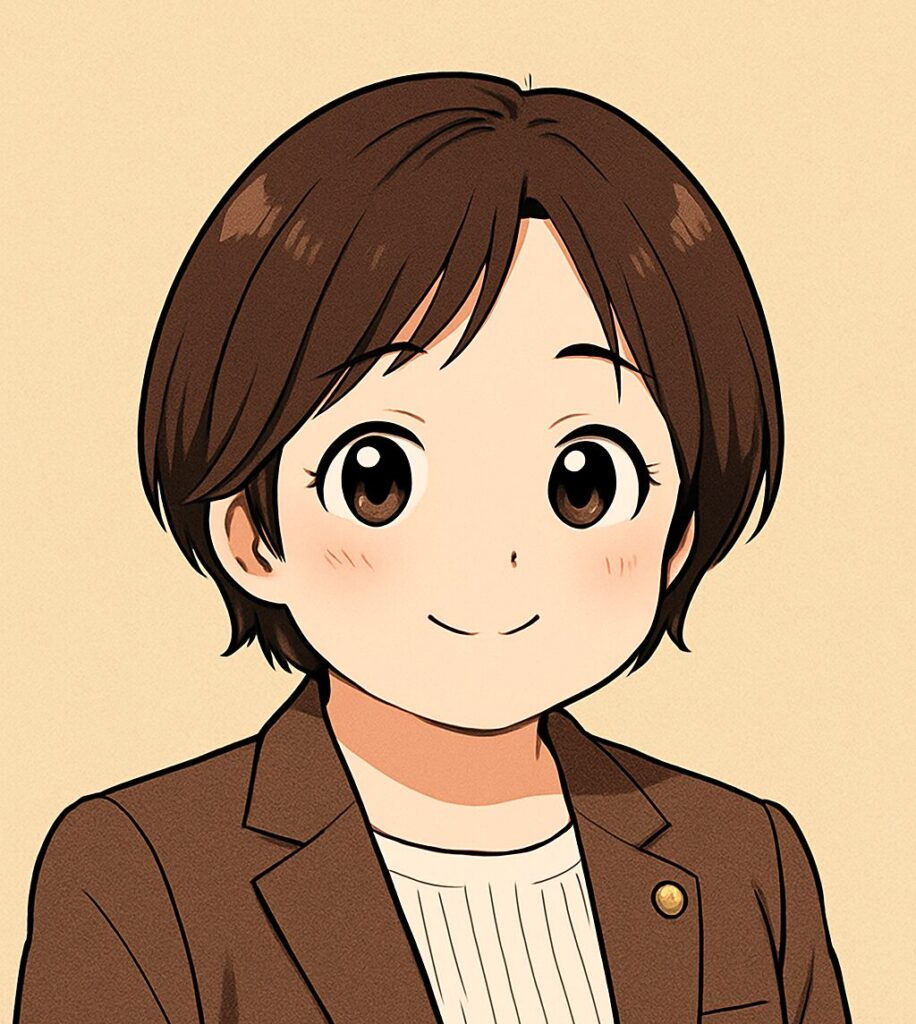税理士会の研修で学んだ「ChatGPTと税理士業務のこれから」
先日、税理士会の定例会研修で、公認会計士・税理士の大野修平先生による
「ChatGPTの基礎と現在 ~税理士事務所での活用を念頭に~」という講義を受けました。
普段の研修は税法や会計基準などの内容が多いのですが、今回は少し異なるテーマ。
「AI」や「ChatGPT」という、これからの税理士業務にも関わる内容で、とても興味深いものでした。
AI時代における税理士の役割とは?
大野先生の講義では、ChatGPTだけでなく、Gemini・NotebookLM・Gensparkなど、 複数の生成AIツールも紹介していただきました。
それぞれの特徴や税理士業務への活用方法を知ることができ、AIの広がりを実感しました。
特に印象に残った3つのポイント
- レシートの画像から自動で仕訳を作成できる機能
手入力が不要で、複数のレシートにも対応できるとのこと。これは記帳業務の効率化に大きくつながると感じました。 - 自分でも簡単に「GPTs(カスタムGPT)」を作れること
実際の作り方まで丁寧に説明していただき、「自分の事務所専用GPT」を作ってみようと思いました。 - スライドを画像つきで簡単に作成できること
今後の「決算法人説明会」などで活用してみたいと思いました。
AIとどう付き合うか?大野先生の言葉
「AIを馬鹿にしたり、避けたり、戦うのではなく、
認めて、使いこなし、役割分担していくことが大切です。」
この言葉がとても印象に残りました。 AIが発達するほど、「AIにどんなことをさせるか」「自分がどんなことをしたいか」を考える力が求められます。 まさに、AIをうまく活かせる人が次の時代に価値を発揮できるのだと感じました。
AIではできない“人の価値”を大切に
ChatGPTを使えば税法の知識や制度は簡単に知ることができますが、
お客様と直接お話しして感じる温度感・信頼関係・経験はAIにはできません。 税理士としての価値は、申告書を作ることだけでなく、 「お客様の想いを理解し、寄り添うこと」にあると改めて感じました。
AIと共に進化する税理士へ
AIを上手に使いこなしながらも、 人にしかできない部分を大切にしていく。 そんな姿勢で、これからの業務に取り組んでいきたいと思います。